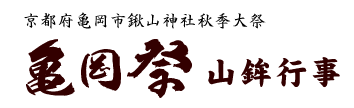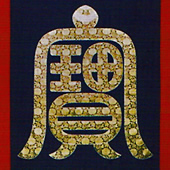蛭子山(塩屋町)

釣り上げた大きな鯛を抱いてニッコリと笑った恵比寿像をご神体とする蛭子山は、旧胴幕に転用された水引幕の銘文から、寛延四年(1751年)ごろに建造されたと考えられています。
現在、伝承されている縣装品は、下水引が明和六年(1769年)、前掛幕・胴幕等は天保二年(1832年)に新調されました。
蛭子山の自慢は西陣大型綴の見送幕です。三人のオランダ人を描いたこの綴織りは、鎖国の時代にあって、外国の風景を題材にした風流の趣の最高潮に達した姿です。
このように、亀岡祭山鉾では、当時の織物のなかでも制作費の一番高い大型綴錦を11枚も揃えており、祇園祭を除く、他地方の追随を許さない町衆の心意気を表しています。
蛭子山の懸装品
- 見送幕
- 絹と麻の綴織「蘭人図綴錦」 天保2年(1831)頃制作。昭和60年(1985)補修。
- 見送下掛下部
- 朝鮮毛綴半裁「五羽鶴図」(18世紀)
- 前掛幕
- 紺羅紗地「宝」字切付刺繍 昭和62年(1987)修理
- 旧胴幕
- 紋綾「雲龍立湧文様紅白綿緞子」 文化6年(1809)
- 旧胴幕
- 繻珍綿「緋羅紗・雲龍立湧文様繻珍綿」 天保2年(1831)
- 胴幕
- 緋羅紗「赤地金襴立継」 昭和63年(1988)修理
- 旧水引裏布
- 未晒麻 寛延4年(1751)未年9月
- 旧下水引
- 金駒繍「緋羅紗地蔓柏紋刺繍」 天保2年(1831)
- 旧天水引
(2枚) - 金襴「赤地柘榴地文様」 江戸後期
- 水引幕
- 金駒繍「緋羅紗地蔓柏紋刺繍」 昭和61年(1986)修理
蛭子山データ
- 所在地
- 塩屋町
- 建造年
- 1751年ごろ
- ご神体
- 恵比寿神
- 高さ
- 3.925m
- 屋根幅
- 2.7204m
- 見どころ
- 見送りがよそと趣が違います。織った人の技術がよかったのでしょうな。昔はかいて町内を回ったもんやが、戦後はしたことはありません。(昭和55年新聞紙面より 前田一夫談)