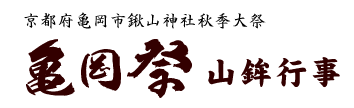難波山(矢田町・京町・上矢田町)(矢田・京・上矢田町)

百済国から渡来した漢の高祖の子孫と伝える「王仁」をご神体としています。この王仁は、『論語』10巻、『千字文』1巻を伝来した人物です。
難波山鉾は、欄縁の箱銘から、安永6年(1777年)頃に舁山として建造されたとされます。また、『引山記』によると、寛政11年(1799年)に曳山として現在の鉾の姿に改装されました。
この改装に際しては、町衆が10年間祝儀、不祝儀、諸普請を問わず、質素倹約に努めることを申し合わせ、経費を捻出したとあります。文末に、「町中が、えいやえいやと、引山に、なおすも神のちからなりけり」とあるように、町衆の結束の強さを伝えています。
難波山の懸装品
- 見送
- 群鶴図表裂正絹綴錦 190年ぶり新調(1982年2月完成)
- 見送
- 高士観瀑図刺繍 寛政11年9月作 平成12年修復完了
難波山データ
- 所在地
- 矢田町・京町・上矢田町
- 建造年
- 1777年ごろ(舁山) 1799年 曳山に改装
- ご神体
- 能楽「難波」の主人公「王仁」
- 高さ
- 10.043m (屋根まで4.917m)
- 屋根幅
- 2.640m
- 見どころ
- 「町中がえいやえいやと引山になおすも神のちからなりけり」