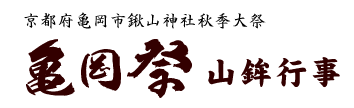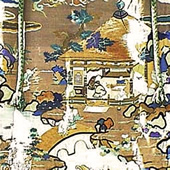三輪山(本町)

大和の国三輪山麓に鎮座する大神神社の祭神である「大物主大神(おおものぬしのおおかみ)をご神体とし、能楽「三輪」の後シテの女神像で表しています。
「古来一社の神秘なり」として、三輪山の大神神社に現存する三ツ鳥居は、全国鳥居多くあれどこの形式は唯一無二のものです。本町三輪山鉾の正面には、澄みきった心身で神に近づく意で、この三ツ鳥居が神門として飾られています。そして、この三ツ鳥居の箱書きから、寛延2年(1749年)に建造されたことを知ることができます。
また、当町に残る「三輪山神記」等によると、当初は舁山として建造されましたが、天明元年(1781年)、曳山の鉾として改装されました。山鉾を飾るイギリス製の胴幕やインド製の見送幕などは、このころに新調されたものです。
亀岡祭は、戦後しばらく中断していましたが、昭和28年ごろに復活し三輪山鉾だけが町内の巡行を続けました。鉾町民の維持、保存継承にかける心意気と未来に向けた不断の努力を、この囃子の音色に感じていただけたらと思います。
三輪山の懸装品
- 見送
- 駒使い繍「ビロード地クルス・鳥唐草文様刺繍」 天明元年(1781)マカオ(18世紀)大正10年修理 平成4年仕立て替え
- 見送下幕
- 綾地錦「紅地菊・龍丸唐草文様錦」 天明元年(1781)マカオ(18世紀)
- 見送下幕
- 繻珍錦「紅地桐・鳳凰唐草文様繻珍錦」 江戸中~後期
- 袖幕(二枚)
- 繻珍錦「紺地雲に龍丸宝散文様繻珍錦」 江戸後期
- 胴幕(二枚)
- 摺込捺染「黄羅紗地獅子と果実文様捺染」英国ヴィクトリア朝(19世紀)
- 前懸
- 綴織「鳳凰に唐子嬉遊図綴錦 文化2年(1805) 平成3年修理
- 下水引(二枚)
- 唐撚繍 金駒繍「霊長文様刺繍・胸背繋」 清朝(18世紀) 平成5年修理
- 旧二番水引
- 繻珍錦「紺地雲に龍丸宝散文様繻珍錦」 江戸後期
- 二番水引
- 紺地金襴 江戸後期 平成4年(1992)
- 見送下幕
- 平成4年(1992)
- 天水引
- 唐撚繍切符「緋羅紗地天女奏楽図刺繍」 天明元年(1781)生地欧州(18世紀)
- 網隠
- 緋羅紗無地 欧州(19世紀)
三輪山データ
- 所在地
- 本町
- 建造年
- 1749年(舁山) 1781年 曳山の鉾に改装
- ご神体
- 大物主大神
- 高さ
- 11.243m (屋根まで5.535m)
- 屋根幅
- 3.279m
- 見どころ
- 囃子の音色